
amphibianです きのう「トガビト」や「鈍色」のトップのディレTに「最近のポータルはつまらん」とか言われて ウボァーギュロギュリラー 的なかんじで 新コーナーを立ち上げることにします
「ライターとゆーオシゴト」では シナリオライターという立場から お仕事のオモシロ話やコツやあるあるネタなど いろいろなコラムを書いていこうとおもいます
だらだら書きます ごしょうらんください
amphibianが最初にものがたりを書いたのは、たぶん小学校低学年時の作文の時でした。リアル友達3組でジャングルを冒険して宝を手に入れる的なお話で、自分が一番活躍するという超絶赤面要素があったものの、がんばって書いた記憶があります。
その次は小学校高学年のころ、PC9801用の「RPGツクール Dante98」(当時は3.5インチと5インチのフロッピー付きムックで売られてました)でRPGを作ろうとしていました。いまかろうじて記憶にあるのは、やはり自分らしき人物が不当に活躍していたことと、敵の組織の名前が「SS(セカイ・セイアツ)」だったということで、あのもうやめていいですか。こいつはフロッピーディスクにうっすら傷がつく昔PCユーザの宿命的現象によりオシャカになりました。
他にもいろいろしましたが、完成したのは、父に提示された「1つでも作品を完成させろ」という条件を満たすために、むりやり「金持ちに捕まった猫が脱出する超短編」だけでした。
中学校のころ、じいさまが放り出したワープロをもらったことで「モノを書く」ことに徐々に傾倒しはじめました。たしか電撃ゲーム文庫の募集を何かのラノベの綴じ込みで見て、「自分で遊びたいゲームの小説を書こう」と思い立ったのがきっかけだったとおもいます(うちにはゲーム機がなかった)。
このワープロを使い、中高生の時期に、長編をじつに3本はトライしています。
- ポストアポカリプス的な世界観で等身大ロボットを操作して戦う傭兵少年たちのお話(未完)
- 「神と魔の中立のものとしてそれらを封印する魔法使い」のおっさんと少女が一緒に旅をするファンタジー(未完)
- 「世界を侵食する世界」におそわれたファンタジー世界の人間が戦うアクションもの(未完)
みごとに一つも完成させられませんでした。
これらは立派な黒歴史となり、いまでもHDDに移されて死蔵されています。
この「等身大ロボットを操作して闘う傭兵少年たち」については特に最初の作品でもあり、好きなジャンルでもあることから思い入れがあったのですが、どうやっても終わらせることができなかったのです。
そのころ両生類はこんなことを思っていました。
「テーマなんて、書き手からの押し付けである」
映画のコピーとかで「テーマは友情!」とかあるだけで反発を覚えていました。自分はそんなものを提示せず、ただ面白いものを書けばいいんだなどと思っていました。
「計画なしで好きなものを書こう」
たくさん書きたいものがありました。自分の想像力はとても優秀で、一つの世界をどんどん広げていくことが楽しく、アイデアが出ては作品に盛り込み、充実していく世界観を作者視点から眺めては悦に浸っていました。
「よくできた嘘があれば、取材なんていらない」
やはり自分の想像力をとても信じていたため、想像力で知識を補完できるとおもっていました。むしろ他のものを見ることは自分のオリジナリティを薄めるのではないかとすら。
「等身大ロボット」の執筆は、困難を極めました。
たくさん兵器を登場させましたが、そもそもマシンガンが秒間数十発の連射性をもつことの優位性を良く知らない。「大企業の圧政」というバックボーンがまったく現実味をもたない。少年が大人よりも活躍することに合理性を与えられない。ヒロインがなぜ主人公を好きになったか分からない。「宿敵」の存在理由として「主人公をいちど挫折させる」という点に気付いたのは良いとしても、挫折した主人公をどう立ち直らせればいいのか分からない。結局「守るために戦う」というウンコのようにありふれた理由をのせてみたものの、面白くない、面白くない、面白くない……
実をいえば「等身大ロボット」は、第二の人類を名乗る謎の超絶クリーチャーまで登場させて一度むりやり完結させてるはずなのですが、納得がいかないままにこねくり回し、結果的に手が付けられない状態になったため、未完と言う扱いにしております。
他の2本はどちらかといえば書くのに飽きてしまって終わったのですが、1本目は明確に、両生類が死なせてしまったのでした。
……
この記事を書くにあたり、「等身大ロボット」のことを振り返ったとき、ものがたりにとってとても大事なことをひとつ見つけられました。
それは、物語をきちんと殺してあげることです。
あえて「終わらせる」でなく「殺す」といいます。
「終わらせる」のは「終わり」とかけばすぐです。しかし「終わってないじゃん」と言われることも簡単です。
みんな、説得力のある死体を見なければ、納得しないのです。
作ったばかりの世界観は、キャラクターたちは、みずみずしく精力的で、魅力的です。
しかしながら、それらはいずれ、作者側の飽きや忘却や成長によって、色あせ、老衰してしまうものです。
作者は責任をもって、彼らが魅力的なうちに、新鮮なうちに、殺さなければならない。
作者は世界の創造者であると同時に、その世界を滅ぼす魔王なのであるべきなのです。
そして、もうひとつ、誰もが知っている、とても大事なこと。
世界を滅ぼすには、遠大な計画が必要です。
どんな魔王だって、回りくどい計画をたてます。そういうのが必要なほど、世界を、物語をひとつ殺すというのは大変なのです。
作者が作った世界は、キャラクターは、物語は、簡単には殺されてくれません。作者がそれを愛するゆえに、彼らはのべつまくなしに輝き続け、魅力を垂れ流しにします。その結果、魅力を使い果たして、未完のまま、死んでしまいます。
だから、彼らが終わってくれるように、きちんと手順をふまないといけません。
世界には、キャラクターには、それぞれ物語があります。それらが一定のこたえに辿りつくことで、ようやく彼らは退場してくれます。小さな物語がバラバラにならないまま、大きな流れになり、やがてクライマックスという山から滝になって流れ落ちる、その破壊力をもってしないと、世界は終わらないのです。
無計画でいいわけがありません。
計画を立てるには、当然方針が必要です。方針のタイプによってたくさんの技法があります。それらをまとめて「テーマ」と呼ぶなら、ぜんぶとても役立つものです。
そして、いいかげんな知識に基づいて作られた武器や舞台や人間関係を与えたところで、物語はみすぼらしい外見のまま、もっと面白くしろと不平不満を言い続け、ほころび、腐っていくだけです。
「鈍色」のとき、原作者さんと「死人が出るのを避けられない物語ですが、無駄な死人は一人もないようにしましょう」と話していました。
思えば、「幾多の死人とともに、一握りの生還者が、ふたたび生きてゆく」という物語の殺し方を、いちばん最初に決めていたのです。
もしあなたが物語を描いているなら、物語は放置すると衰弱死するということは、覚えておいて損はないとおもいます。
新鮮なうちに、適切な方法で、殺す。
その素晴らしく完成された死体こそが、読者に見せるべきものなのだと。
それを忘れないことを、おススメします。
もうひとつ。
殺しそこなった物語も、捨てずにとっておいてください。それはあなたの失態の証拠であり、あなたにはそれから何かを学ぶ責任があるのです。
どーでしたでしょうかー だらだらすぎてびみょうかなあ
これ書くために黒歴史を掘り起しすぎました うぇっぷ
反響があるようなら つぎは今回もちょっと触れた ものを書くうえでの「取材」について書こうかしらん? なにか興味があることがあれば コメントしてくださいねー









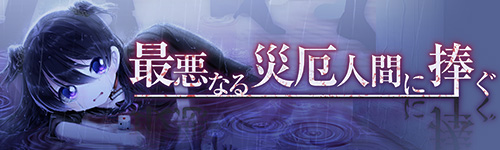





殺すという言葉はショッキングですが、
終わらせるという点では共感しました。
山場のために手を尽くして、引き際をわきまえるというのは、
一次創作の特権じゃないかしらん。
キャラの肉付けは二次でもできる、
一次は世界の屋台骨を作って欲しい、
一番見せたい山場を見せて欲しい、
と進行形で腐らせてる人が言ってます。
Dante98は年がバレます、ツクールとか濁しておきましょうぜ。
憧れだったよDante98、PC98なんて手がでなくてスーファミ版だったよう……。
声だして笑ったあとに考えさせられました。
こういうことを考えてらっしゃるからこそ、例えば鈍色なら、すぐに死んでしまった巴に対しても、とっても感情移入しようとしてしまうんですね。
とりあえず、自分の書いた黒歴史は取っておくことにします。